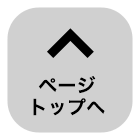ポカポカと気持ちのいい日がやって来るのは嬉しいものの、目や鼻がムズムズしてきたという人も多いかもしれません。
イヤ~な花粉症の到来です。お化粧してもマスクで台無し、せっかくのアイメイクも目のかゆみでぐちゃぐちゃ。女子にはツライ時期ですね。
そこで、花粉症に効く薬について調べてみました。気になるお金の面についても確認してみましょう。
花粉症の市販薬はこれ!
セルフメディケーション税制で
花粉シーズンを乗り切る
2018年2月21日

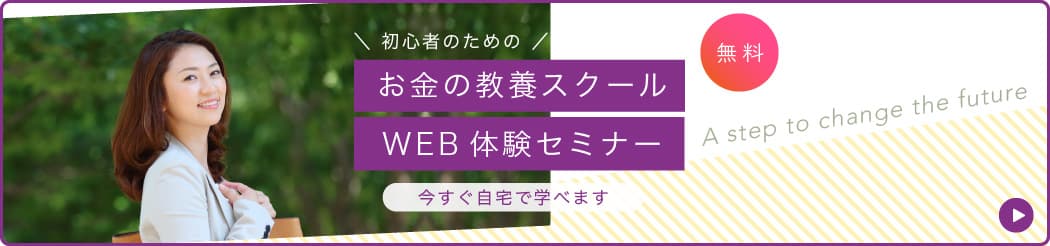
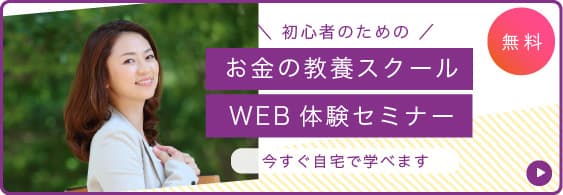
気をつけて!花粉はもう飛んでいる!

いまや国民的症状ともいわれる春の花粉症。原因とされる花粉の代表がスギ花粉だということはあなたも知っているでしょう。
スギ花粉の飛来時期は気温に由来するところが大きいとされ、年や地方によっても変動するようです。
環境省の資料「花粉症環境保健マニュアル-2014年1月改訂版-」によると、スギ花粉の飛来は広い範囲で1月から始まるよう。
そのうち1日あたりの飛来量が50.1個/cm2以上とされる、統計上最も多い飛来量が続く時期は、たとえば関西地方では2月後半から3月いっぱい、東北地方が2月後半から4月中旬にかけて、そして関東地方では2月はじめから4月いっぱいと丸3ヶ月間で最も長期に及びます。
あなたの地域のより具体的で日常的な花粉飛散状況は、「環境省花粉観測システム(愛称:はなこさん)」で確認できますよ。
こんな日、こんな時間帯に花粉が多くなる!
先に見た花粉飛散期間中でも、次のような天気になると花粉が特に多くなるそう。
- 晴れて、気温が高い日
- 空気が乾燥して、風が強い日
- 雨上がりの翌日や気温の高い日が2~3日続いたあと
また、スギ花粉が多くなる時間帯は、その日の気象条件によって変わるものの、一般的には、気温上昇で朝スギ林から飛び出した花粉が都市部に到達する昼前後と、上空に上がった花粉が地上に落下してくる日没後に多くなると考えられているのです。
ムズムズ辛い症状への対策は?

これまでの文章を読み、花粉という言葉を聞いただけで鼻がムズムズしてきたという人も多いかもしれませんね。
そのとおり、花粉症ではくしゃみ、鼻水、鼻や目のかゆみなどが主な症状です。
想像するだけで身体が反応するということはありそうですが、正確には花粉症は体内に入った花粉に対して身体が起こす異物反応。
すでに花粉症を発症している人も、予備軍、まだまだ縁がない人も、体内への花粉の侵入をブロックすることが何よりの予防対策です。
花粉の飛散状況などを知り、マスクやメガネで予防すること。花粉の多い時間帯の外出には、花粉が付着しにくい衣服にするなどの心がけも大切でしょう。
帰宅後には洗顔やうがいで花粉を洗い流すことも有効とされています。
医学的な治療法は?
「毎年この時期になるとツライ…なんとかしたい!」というあなた。医学的な治療を受ける方法もあります。
厚生労働省の花粉症対策に関する情報によると、花粉症の治療には、医療機関で行う薬物療法、手術治療、減感作療法などがあるそう。
そのうち完治が可能とされる減感作療法(抗原特異的免疫療法)でも現在の治療法では、完治する率は決して高くなく、実施している医療機関も少ない状況のようです。
つまり、症状や重度に合わせ、経口薬、点鼻薬、点眼薬などの薬を用いる方法が一般的のよう。
花粉症対策にもセルフメディケーション!

2017年にスタートしたセルフメディケーション税制は、花粉症対策にも活用できそうす。
厚生労働省で指定されたセルフメディケーション税制対象のOTC医薬品にも花粉症に効果的な経口薬、点鼻薬、点眼薬なども含まれているんです。
よほどの重症でなければセルフメディケーションで対策することで、医療費の節約にもなりますね。
たとえばどんな薬?
具体的な商品名は省略しますが、いわゆる花粉症を含むアレルギー症状専用の飲み薬、点鼻スプレー、目薬などがあります。
たとえば、急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎からくるくしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛みなどを緩和する服用剤。炎症を鎮めながらアレルギー症状を抑える花粉症専用の点鼻薬。
花粉・ハウスダストなどによるかゆみ、炎症などを鎮め、炎症により傷ついた目の状態を整える目薬等々です。
日頃の健康管理が花粉症対策に!
花粉症はアレルギー症状ですが、鼻粘膜の状態をよく保つことで、その予防や緩和に効果があるそう。
睡眠不足やストレス、飲みすぎなどが悪化の要因だから、規則正しい生活習慣を身につけ、健康管理に努めたいですね。
そもそも自発的なセルフメディケーション(自主服薬)に取り組み、健康の維持増進と疾病の予防環境整備を行うこと、そして、そのための費用に対して優遇税制という形でサポートすることがセルフメディケーション税制の目的です。
セルフメディケーション税制についての詳細は「健康管理が節税に?!新しく始まったセルフメディケーション税制って?」の記事でも確認できます。
花粉症の人はもちろん、花粉症でない人も、疲れやストレスを溜めないように、セルフメディケーション税制を上手く活用し、日頃からの健康管理をしながら花粉症シーズンを乗り切りましょう。