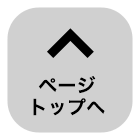入院や死亡によってお金が必要になった場合、本人が銀行に行けないので、本人以外の人に引き出しをしてもらわないといけません。どんな時に、どんな条件で引き出しができるのか、また、その場合に備えて事前に何をしておけばいいのかお話します。
銀行窓口で本人以外が引き出すのはこんな時。
事前にやっておくことは?
2020年2月1日

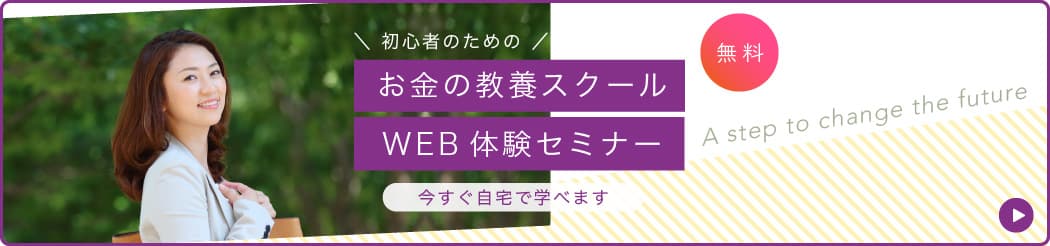
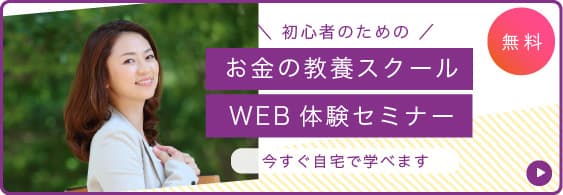
本人以外が引き出すケースとその条件
銀行口座から本人以外が引き出すケースとしては、本人が災害に遭った時、本人が入院してしまった時、本人が介護状態になった時、本人が死亡してしまった時などが挙げられます。
本人以外が引き出す場合の条件は、引き出す理由や銀行によって対応が少しずつ異なっていますが、主に以下の通りです。
誰が引き出すことができるか
「親族」としているのが一般的ですが、生活費のための引き出しであれば同居人に限定、葬儀費用のための引き出しであれば法定相続人に限定、本人が病気や高齢で来店できない場合は親族であればよしとするなど、状況や銀行により「親族」の定義がさまざまです。
どんな書類が必要か
原則として本人の通帳、届出印、代理人の本人確認ができる書類、親族であることが確認できる書類、委任状などが求められ、本人が死亡時の場合には死亡診断書も求められます。しかし、災害時などやむ得ない事情の場合は行員の判断によりますし、委任状があっても、本人に確認の電話などが行く場合もあります。
いくらまで引き出しできるか
10万円までとしていることが多いです。本人が従業員に給与の支払いをしなければいけないなど事情がある場合は行員の判断によって、葬儀の場合は適当とみなされる葬儀費用とすることもあります。
相続の場合、以前は遺産分割協議が終わるまで引き出しができませんでしたが、2019年7月に法改正があり、預金残高の3分の1までについて法定相続割合まで引き出しが可能になりました。(上限150万円)
いずれの場合も銀行の窓口で事情を説明し、妥当であると認められるかどうかによります。引き出しが必要になった場合は、自分と本人の間柄、なぜ引き出ししなければいけないのか、いくら必要なのか、などをきちんと窓口で事情説明しましょう。
事前準備としてできること
上述のように、本人以外でも引き出しは可能ですが、手続きに書類を用意したり、上限額が決まっていたりなど、不便なこともあります。
これを避けるためには以下の事前準備をしておくとよいでしょう。
自分が本人で、誰かに代理を頼む場合
ある程度現金を手元に置いておく:いざという時に備えて、お財布に多めに現金を入れておくと、災害や事故に巻き込まれた場合でも自分で対処できますし、現金を家においておくと、家族はわざわざ銀行に行くことなくすぐに使うことができます。
キャッシュレス化:長期で入院するような場合でも、光熱費などの支払いは口座引き落としにしたり、ネット銀行からの送金、カード決済にすることで病院にいても支払いを済ませることができます。
入院時は限度額適用認定証をもらう:手続きをしないまま入院すると、一旦病院の窓口に3割負担の入院費用を支払い、高額療養費の支給申請をすることで上限額を超えた分が還付されるという流れになります。しかし、事前に限度額適用認定証をもらっておくと、最初から自分が負担する分だけ支払えばよくなり、3割負担分が高額になりそうな場合にはかなり便利です。
銀行は行きやすいところにまとめておく:どうしても代理人に銀行に行って引き出してもらわなければいけない場合を想定して、銀行はわかりやすいところにすることをおすすめします。そして、確実に残高があるように、たくさん口座を作るよりもある程度まとめておくことをおすすめします。
葬儀費用分は残しておく:葬儀費用に関しては上限が10万円ではなく、かかる費用分を引き出しさせてくれることが多いので、費用相当分を残しておくと遺された遺族が助かります。
自分が「本人以外の場合」
親に伝えておく:自分が代理になるとしたら親の代理になる可能性が高いと思いますが、上述の自分の場合の事前準備を親にも伝えておくと、いざ自分が代理をしなければいけなくなったとき助かります。
日頃から銀行に自分が代理人であることを知らせておく:親が高齢の場合など、普段から親が銀行に行くときにできるだけ同行して、自分が親族であること、親のサポートをしていることを見せておくと、代理で銀行に行った時も手続きがしやすくなります。
立替分を用意しておく:銀行からの引き出しだけでは十分ではない場合に備えて、自分の口座から立て替えとして引き出せる金額をいつも持っておくと慌てずに済みます。
そして、いざという時慌てないように、自分が本人の場合、代理の場合について、親子間で話し合いをしておくことをおすすめします。
(※本ページに記載されている情報は2020年2月1日時点のものです)