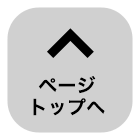お金は増やしたい!でも、資産運用して元本割れにはしたくない!・・・そんな安全重視の人は無理にハイリスクの投資をすることはありません。ローリスク資産運用がいい理由や、元本割れしない、あるいはローリスクでできる資産運用についてお伝えします。
「絶対安全派」のための
ローリスク資産運用講座
2020年1月14日

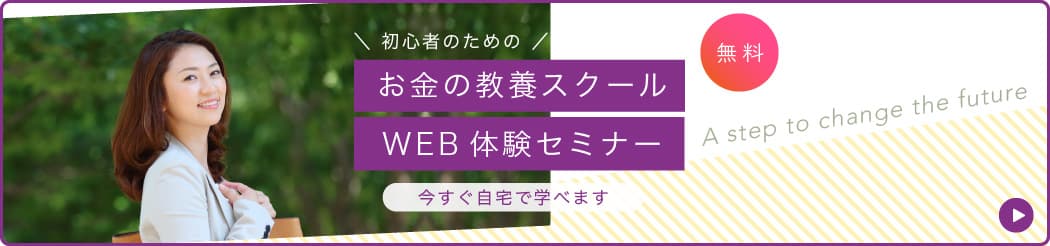
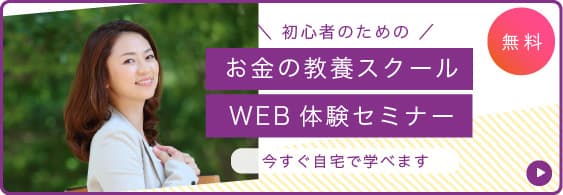
安全志向でもいい理由
資産運用において、安全志向でいい理由には以下の2つがあります。
今の日本は低成長
厚労省「勤労統計」によると、お給料の総額である名目賃金から物価上昇率を差し引いた実質賃金は、2018年では0.2%増であると発表されました。そして、総務省の「物価指数予測」によれば、平成時代30年間の物価は大きな変化はなく、今後10年間の見通しも0.5%程度の上昇率とみられています。つまり、今のお仕事を続けていれば、物価の上昇はあるもののお給料の上昇率の方が高いので、現状の生活を維持できるということです。
今後の不安材料として、高齢化による社会保障費の上昇、その財源として消費税増税なども考えられますが、一方で労働力不足のために雇用期間延長で収入増なども考えられます。
現在の物価が安定していて、将来どうなるかわからないからこそ、リスクの高い金融商品を選んで資産を減らすよりは、確実に貯蓄額を増やしていける商品を選ぶ方がいいのです。
お金は守りが大事
富裕層の相続対策、節税対策などよく聞くと思いますが、彼らはお金を増やすよりも減らさないことを大事にしています。お金を増やすにはコツコツ時間をかけなければいけませんが、守りが甘いとあっという間にお金はなくなってしまうからです。これは、資産をたくさん持っていなくても同じことです。
そして、富裕層の場合は、攻めのための余裕資金がありますが、余裕資金がない人は、減っても困らない資産はないので「守り」でなければいけないのです。
おすすめローリスク商品
では、安全に資産運用できるローリスク商品・ノーリスク商品について見ていきましょう。
銀行預金
銀行預金は1,000万円とその利息までは元本保証されるので、用途によって使い分けながらいくつか持たれておくことをお勧めします。
「定期預金」は原則として満期まで引き出しができませんが、普通預金よりも利率が高いというメリットがあります。短期のものもありますのである程度まとまったお金があるのであれば、定期預金にすることをおすすめします。毎月コツコツ貯金していきたいのであれば、「積立定期預金」、1,000万円以上のまとまったお金があるのであれば「大口定期預金」がおすすめです。
いつでも引き出したいのであれば、「貯蓄預金」がおすすめです。一定以上の残高があれば、普通預金よりも利率が高くなります。
また、当座預金は利息が付きませんが、銀行が破綻しても全額保護されるというメリットがあります。
外国通貨のものは金利が高いですが、為替リスクがありますのであまりおすすめしません。
個人向け国債
国の借金なので元本保証ではありませんが、日本が財政破綻しない限り償還されるため、比較的安全です。
1万円から始められ、年2回利払いがあるというメリットがある一方、満期が3年、5年、10年と比較的長いので、すぐに換金できないというデメリットがあります。途中で売却した場合は、その分利子も減りますので、注意が必要です。
貯蓄型保険
「養老保険」のように死亡保障とともに満期が来たら満期保険料が受け取れるもの、「個人年金保険」のように一定期間保険料を払い込むと老後、年金形式で保険金が受け取れるもの、「終身保険」で一定期間過ぎると解約返戻金が払込保険料を上回るものなどがあります。
いずれも、長期間の契約で、途中解約をすると払い込んだ保険料がほとんど戻ってこないなどデメリットがありますので、継続して保険料を払い続けられるか十分に考えてからにしましょう。
iDeCo
政府が国民の資産形成のために作った制度なので、比較的安心・安全ですが、自分が加入している年金制度によって加入できない場合もあることと、掛け金が決まっていることを確認しましょう。
商品は比較的リスクの少ない投資信託を中心に集められていますので投資信託を選んでもいいですし、どうしても心配な方は定期預金を選ぶこともできます。
掛け金を全額所得控除することができるのでおトクですが、途中でやめたくなった場合、掛け金を休止することはできても引き続き手数料がかかることと、60歳まで引き下ろすことができないのは注意が必要です。
ミドルリスク商品を始めたくなったときの注意事項
このような商品を活用して安全に資産を守っていくのもいいですし、ある程度慣れてお金も貯まってきて、もう少しリスクを取ってもいいと思えるようになった場合は、iDeCoやつみたてNISAの商品に挙げられているような手数料の低い投資信託から始めてみることをおすすめします。
(※本ページに記載されている情報は2020年1月14日時点のものです)