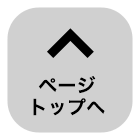女の子がいるご家庭では桃の節句のひなまつりをお祝いしますよね。ひなまつりの由来を知っておくことで、子どもにより健やかに育って欲しい親の気持ちが伝わります。大切な1日を演出するために準備もしっかり行っていきたいですよね。年に1度の大切なイベントを素敵な思い出にするため、ひなまつりの由来やお祝いの仕方をお伝えします。
3月3日はひなまつり♪
ひなまつりの由来と祝い方
2019年2月28日

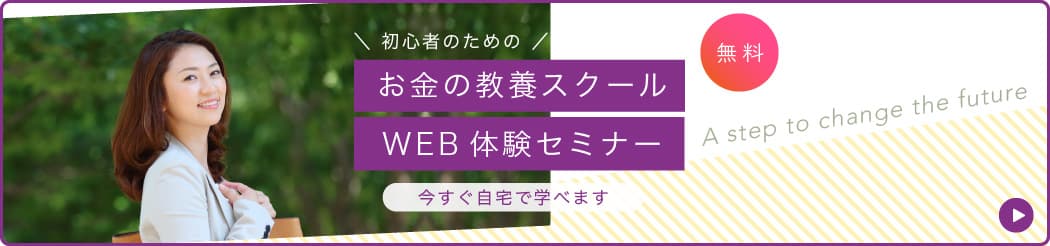
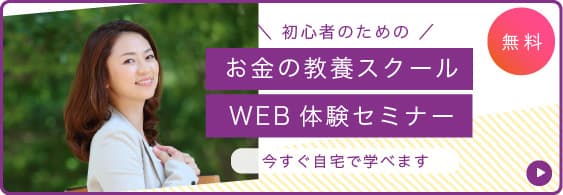
ひなまつりの由来

現代では3月3日のひなまつりといえば「女の子の日」としてお祝いしますが、日本に伝わった頃はそうではなかったようです。いつ頃日本に伝わり、当時はどのように祝っていたのか、ひなまつりの由来をご説明します。
季節の節目の前日が節句
日本には五節句といい5つの節目があります。それぞれ1月7日人日(じんじつ)の節句、3月3日上巳(じょうし)の節句、5月5日端午(たんご)の節句、7月7日七夕(しちせき)の節句、9月9日重陽(ちょうよう)の節句です。
この3月3日上巳の節句が現代の桃の節句、ひなまつりにあたります。平安時代頃に中国から伝わり、3月はじめの巳の日に子どもの無病息災を願い、邪気払いを行う風習がありました。
平安当時は女の子だけの行事ではなかった
平安時代当時は、子どもの死亡率も高かったため、草やワラで作った人形を身代わりとし厄払いをした後、川に流す風習(流し雛)もあったそうです。子どもの厄払いという意味があり、男女共通の行事とされていました。
女の子の行事となって行く過程となったのは、貴族階級の女児たちの間で人形遊びがはやり、その遊びが「ひいな遊び」と呼ばれ親しまれていたことが女の子の日となるきっかけになります。その後、室町時代に流し雛ではなく家で飾るようになり、江戸時代に入ってからは、幕府が上巳の節句を3月3日と定め現代のひなまつりとなって行きました。
現代のひなまつり事情

「ひなまつりが3月3日とは知っているけれど、ひな人形っていつ頃出していつ頃片付けるの?」、「毎年ひな人形の並べ方に困る!」、「ひな人形っていくらするの?場所が取れないからシンプルなものはあるのかな?」
年に1度のイベントだからこそきっちりとお祝いしたいものの、年に1度だからこそ曖昧になっている部分も多いですよね。この機会にぜひ確認してみてください!
ひな人形を出す時期、片付ける時期
・ひな人形を出す時期
一般的に立春を迎えてからといわれています。立春は2月3日節分が過ぎた次の日です。地域によってはお正月の松が明ける1月8日以降であったり、旧節句を採用している地域では3月の春休み頃に飾る地域もあったりします。
また立春ではなく、二十四節気のひとつである雨水(うすい)にひな人形を飾ることで良縁に恵まれるという言い伝えから、雨水に飾るところもあるそうです。雨水は毎年2月18日、19日頃にあたります。
・ひな人形を片付ける時期
「ひな人形を片付ける時期が遅くなると、お嫁に行けなくなるよ」と1度は耳にしたことがありませんか?この言い伝えには根拠はなく、「出したものはきちんと片付ける。整理整頓ができるお嫁さんになりなさい」というしつけの一環として伝わる風習です。
一般的にひな人形を片付ける時期は、ひなまつりが終わってから2週間を目途にした大安吉日といわれています。しかし大安吉日にこだわらず、カビ予防のために湿度が低いよく晴れた日を選ぶ人も多いです。片付けている時期の方が長いからこそ天候は大切ですね。
ひな人形の並べ方
・1段目親王の段:京都や一部の関西を除き、向かって左側に男雛、右側に女雛
お内裏様とお雛様の飾り位置は、本来ならどちらでも良いそうです。しかし、時代の流れとともに「右にならえ」や「右に出るものはいない」と右が上位である言葉が増えたこと、また昭和天皇が即位された時に天皇陛下の左側に皇后様が並ばれたことからひな人形も左側に女雛を置くようになったそうです。
・2段目:3人官女の段
口が開いている官女が向かって左側、座っている官女が真ん中、口が閉じている官女が向かって右側となります。
・3段目:五人囃子(ごにんばやし)
向かって左から、太鼓、大鼓(おおつづみ)、小鼓(こつづみ)、笛、謡(うたい)の順に配置します。並び方のポイントは、音が大きいものほど左側に置くことです。
・4段目:随臣(ずいしん)
右大臣と左大臣にあたる人形で、若者が右大臣で向かって左側、ひげのある老人が左大臣で向かって右側に配置します。
・5段目:仕丁(じちょう)
仕丁とは雑用係のことで衛士(えじ)ともいいます。怒り顔の仕丁が向かって左側、泣き顔の仕丁が真ん中、笑い顔の仕丁が向かって右側になります。
・6段目:お道具
向かって左側から簞笥(たんす)、挟箱(はさみばこ)・長持、鏡台、針箱、火鉢、茶道具の順に配置します。
・7段目:お道具
向かって左側から御駕籠(おかご)、重箱、御所車を配置します。
最近のひな人形事情
一昔前であればひな人形の7段飾り、5段飾りも見受けられましたが、近頃の住宅事情では中々置き場所に困りますよね。また予算の都合もあります。最近ではコンパクトタイプのひな人形に人気があります。
お内裏様とお雛様2体だけの親王飾りや3人官女までの出飾りに人気があるようです。立春から出すとすると1ヶ月以上飾ることになるためホコリから守るためにケース入りのひな人形も人気となっています。このようなコンパクトタイプのお値段は10万円~30万円くらいが相場となっています。
ひなまつりの祝い方

ひなまつりにはちらし寿司、お吸い物、甘酒、ひなあられなどでお祝いをした人も多いのではないでしょうか?ひなまつりのお祝いで使われる食材にも理由があります!
ちらし寿司
ちらし寿司には長寿の意味があるエビを使用したり、将来の見通しが良いレンコンを使ったり、子だからに恵まれるイクラを使ったり、縁起の良い食材を沢山使えることからちらし寿司を作る家庭が増えたようです。
ハマグリのお吸い物
ひなまつりにハマグリのお吸い物を使う理由は、ハマグリが二枚貝であるためとても縁起の良い食材とされているからです。対になった貝がぴったりと合うことで仲の良い夫婦をあらわしています。また二枚貝にはお姫様をあらわす意味もあるようです。
ひなまつりの由来についてとお祝いの仕方はいかがでしたでしょうか?年に1度の大切なイベントをきちんと意味も知って子どもにも教えてあげたいですよね。