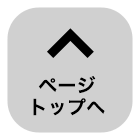2019年平成最後のお正月が訪れました!おせち料理を食べる人が少なくなっている現代。あなたはどうですか?おせち料理は先人たちの知恵が沢山詰まった幸せ料理です!何気なく食べていた人も食材にまつわるエピソードを知ることで、その食材や自然の恵みにも感謝し、幸せを引き寄せる体質になります!
意味を知るともっと美味しい!
もっと幸せに♪
おせち料理のエピソード
2018年12月27日
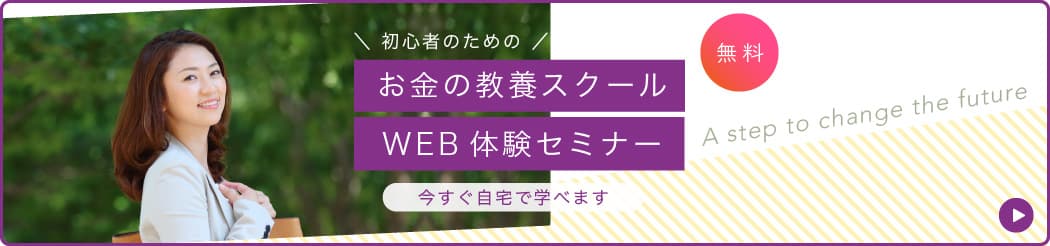
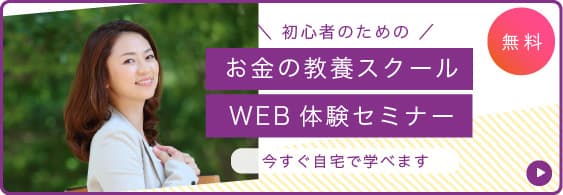
おせち料理の由来
お正月になると食卓に並ぶおせち料理。豪華なお重に入った食材は彩りも鮮やかで新年のお祝いにぴったりな日本の伝統料理ですね。そんなおせち料理ですが歴史をさかのぼると奈良時代~平安時代頃に始まったといわれています。
奈良・平安時代は朝廷内のお供え物だった
中国から伝わった五節句の行事に由来するものがおせち料理です。漢字で書くと「御節料理」と書き、現代の元旦(1月1日)、ひな祭り(3月3日)、端午の節句(5月5日)、たなばた(7月7日)、重陽(9月9日)の5つの節日に五穀豊穣の感謝を神様に伝える宮中行事として始まりました。
現代の原型は江戸時代から
奈良時代や平安時代は朝廷内で節句の祝い事が行われ、一般庶民にはまだ浸透していませんでした。一般庶民にこの節句の祝い事が広まったのは江戸時代頃だといわれています。その年の豊作を願って1年の最初の日に祝い膳として食べられるようになりました。
おせちの食材と重箱
おせち料理に入っているさまざまな食材は、縁起が良いとされゲン担ぎの意味があります。食を通して家族や大切な人を守りたいという思いは今も昔も変わりませんね。
おせち料理を重箱に詰める理由は、めでたさを重ねるという意味を持ちます。一般的に紹介されているのは4段重ねですが、三段重ねや五段重ねといった地域もあります。その地域の風習により重ねる数や詰める料理は異なるため、これが正しいというルールはありません。
重ねた時の上から順番に「一の重」、「二の重」、「三の重」、「与の重」、「五の重」と呼びます。四は忌み数といい、不吉を意味する数字のため用いることを控えています。
おせち料理の中身
一の重
一の重は重ねた時に、1番上にくることから祝い事にふさわしい祝い肴(数の子、黒豆、田作り、たたきごぼうなど)を詰めます。
・数の子
卵の数がとても多い数の子は子宝に恵まれ、子孫繁栄を願う縁起物です。
・黒豆
黒豆は邪気を払う魔除けの意味があります。まめに働き続けられますように。と無病息災を願い詰められます。
・田作り
田んぼを作る。という意味で五穀豊穣を願う縁起物です。田作りは別名ごまめ(五万米)とも呼ばれています。干した片口イワシの稚魚を醤油風味の飴炊きにしたものです。
・たたきごぼう
地中深く根をはっているごぼうのように、我が家も地に根をはって代々栄えるようにとの願いがあります。また、ごぼうの色や形が豊作の時に飛んでくると伝わるタンチョウを連想させることから豊作を願って食べられます。
二の重
二の重には口取り(かまぼこ、伊達巻き、栗きんとんなど)甘い物を中心に詰めます。
・かまぼこ
かまぼこの半円形は日の出のように見え、新たな門出を祝う意味があります。また紅はめでたさと喜び、白には清浄の意味があり縁起の良いものとされています。
・伊達巻き
伊達巻きの形が巻物に似ていることから、学問や習い事、文化の発展を願って詰められます。諸説ありますが戦国武将の伊達政宗が派手好きであったことから「伊達」には華やかさ、派手といった意味もあるようです。
・栗きんとん
栗きんとんの色を黄金色に輝く財宝にたとえ、金運を高める縁起物とされています。
三の重
三の重には酢の物や焼き物を詰めます。現代は縁起の良い海の幸の焼き物を中心に詰められています。
・ぶり
ぶりは成長するにつれ名前が変わる出世魚です。ぶりのように出世を願って食べられます。
・海老
腰が曲がっている海老のように、腰が曲がるまで元気に長生きできることを願っておせち料理に使われます。
・たい
めでたいの語呂合わせです。七福神の恵比寿様が持っている魚であるため、祝いの席にふさわしいとされています。
・ちょろぎ
シソ科の多年草の植物です。漢字で長老喜、千世老木などと書かれ長寿を願い食べる意味があります。
・酢レンコン
たくさん穴の空いているレンコンは、将来の見通しが明るくあるようにと願われ詰められます。
・紅白なます
祝儀袋などに使われる水引が由来です。平和や平安を願う意味があります。
与の重
与の重には山の幸を中心に煮ものや、煮しめを入れます。煮しめには家族が仲良く結ばれる意味があります。
・さといも
親芋に沢山子芋がつくことから、子孫繁栄を願って煮ものとして食べます。
・手綱こんにゃく
こんにゃくを手綱に見立て、1年をしっかりと過ごせるようにとの意味と、結ばれているこんにゃくから良縁に恵まれる縁起物とされています。
・たけのこ
成長の早いたけのこにあやかり、子供がたけのこのように天に向かって出世するようにとの願いがあります。
・くわい
成長過程で大きな芽を出すくわいのように、出世を祈願した食材です。また黄色に色づけしたくわいは財宝を意味します。子孫繁栄の意味もあります。
五の重
五の重は、年神様からの福を詰める場所、今後も栄えるための空きスペースとして空にしておきます。
おせち料理は祝い料理の他に女性を休ませる意味もあった!
最近はローストビーフやハンバーグなど味も濃く、子供も喜ぶおせち料理を見かけますが、昔から食べられている食材には家族の健康や繁栄を願うたくさんの意味が込められていました。
またお正月にやってくる年神様は火を嫌う性質があったことと、せっかく神様をお迎えするのに、水や火を使う炊事仕事は失礼に当たるとして、お正月は料理をすることを控えていたようです。
さらに、毎日毎日家事をする主婦を休ませる意味もあり、おせち料理は保存のきく調理方法や食材を中心に詰められているそうです。
(※本ページに記載されている情報は2018年12月27日時点のものです)